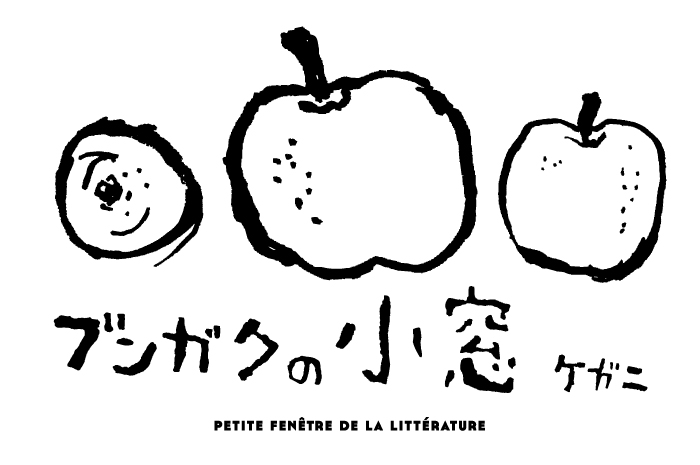どういうときに使うか
サイファー、カンゴールハット、グラフィティ……。ヒップホップ文化がようやく一般化し、長い間日の目を見なかった「日本語ラップ」にも光が当てられるようになった。RHYMESTER宇多丸が地上波テレビでコメントし、サイプレス上野がCMに出演し、園子温監督のヒップホップ映画『TOKYO TRIBE』が公開された。日本におけるヒップホップはここ十年でもっとも動いた音楽シーンの一つではないだろうか。このことは日本語ラップのさらなる複雑化をもたらした。リリック(歌詞)自体も反社会的な内容もあれば詩的で文学的なものもある。英詞のように子音を強調するものや、日本語的な音感を重視するものなど、「フロウ」も多様化した。

この「フロウ」という語は英語やフランス語などでも共通のヒップホップ語として用いられている。ある意味でポエトリー・リーディングの一つでもあるラップ、その鑑賞方法として非常に特殊な要素がこの「フロウ」だと思う。今回はこの語を扱ってみよう。
抑揚、グルーヴ
「フロウ」とは、簡単に言えばラップの抑揚のことである。
flowという英語からわかる通りもともとは「流れ」を意味する言葉で、ほかにも「キャッシュフロウ(企業に出入りするお金の流れ)」や「ワークフロウ(企業での一連の業務の流れ)」などと用いられる。派生語としてはたとえば、「(言葉などが)流ちょうな」という意味のfluentがよく知られている。
だが、ラップの抑揚としての「フロウ」はちょっと不思議な意味を持っている。ほかの音楽ジャンルでいえば「グルーヴ」のようなニュアンスだ。ちょっとしたリズムのよれや、韻の踏み方、発音のメロディをこの言葉ひとつで表すことができる。滑舌の良さに限らず、むしろ滑舌の悪さをフロウと呼ぶこともあるのだ。こうしてみれば、ラッパーの個性そのものがフロウであると言える。
これはラップの詩の朗読としての側面を示している。文学としての詩は、近代以降の印刷技術の発展に伴って「書」で伝わるものであったが、文字を伝えづらい時代においては朗読会や吟遊詩人の歌のように「音」で伝わるものであった。ある意味で、ラップはこの原初の詩の在り方を踏襲していると言える。
(この点、長谷川町蔵、大和田俊之著『文化系のためのヒップホップ入門』(アルテスパブリッシング)では「ヒップホップとは何か」という問いをもっと掘り下げている)。
フロウの傾向性
ところで、ラップの「フロウ」が詩とは異なるのがビートの存在である。ヒップホップのビートはファンク以降、細かい音符をシンコペーションで強調するいわゆる「ハネた」リズムを継承して、その代わりメロディを単純化することで発展してきた。そのためこのビートにいかに言葉を乗せるかが重要な要素となっている。普通の詩よりも韻(ライム)を意識させることで発音の面白さを聞かせるラップは、ビートに対してどこでどのように韻を踏むかのフロウの面白さという――ほとんど唯一の――ルールによって定義されるわけだ。

ただし、今の日本においてこのフロウの個性には一定の傾向が出てきていると思う。それはこのラップ文化浸透の最大要因のひとつとなったテレビ番組、「フリースタイルダンジョン」に端を発するものだ。この番組では、ラッパーがフリースタイルバトル(即興ラップバトル)で競い合い、どちらがいいフリースタイルを披露できるかを競う。かわるがわるラップするわけだから普通のラップよりも小節数に限りがある。歌詞が文字で読めるわけではないので、審査員にアピールするために韻をたくさん踏む必要が出てくるし、その韻も分かりやすい方がいい。その結果、いいフリースタイルとされるものは基本的にはそうした「韻が固い」ものが多いのだ。自然に基本的に滑舌の悪さは嫌われるし、内容で競う言葉遊びの要素が強くなってくる。こうしてフロウが傾向性を持つようになっているのではないだろうか。
フリースタイル以外のフロウ
もちろんこうして短い時間で、大衆に訴えかける言葉の力を最大化できるフロウも魅力的だ。だが、フロウの良し悪しはこうした能力だけで決まるわけではない。すでに述べたようにラッパーがそれぞれ持っているはずの個性がそのままフロウを作り出すのだから、その「独特さ」も面白がられてしかるべきだ。
古い話で言えば、ZEEBRA(キングギドラ)がKj(Dragon Ash)のフロウを自身のコピーだとして告発する曲を書いたという事件もあった。これは僕の理解する限り、「誰かの真似ではない自分のフロウを持つべきだし、それこそがラップの醍醐味だ」という批判だった。また、個人的に思い出深いのは、当時FM802という大阪のラジオ局で「ミュージック・フリークス」という番組を持っていたKREVAが、デビューして間もない無名のラッパー、HUNGER(GAGLE)のラップを、「こいつのフロウはなんか変だけど引っかかるんだよね」などと紹介していたことだ。その後かかった曲の中での、HUNGERの類まれな滑舌と発音の癖は聞いていた僕の耳から離れなかった。もちろんその後のGAGLEの快進撃については言うまでもないだろう。

決してラップは――他の音楽と同じように――単にその技巧だけが評価されるべきものではない。フロウの個性やそこに含まれるラッパー自身の生が言葉のひとつひとつに息を吹き込むのだ。それこそがラップの文体であり創造性なのであるとすれば、フロウとは、ラッパーの生という「流れ」そのものがビートに乗ったもののことを言うのではないか。
illustration by 高石瑞希
今までのブンガク語
第一回:不条理
https://portla-mag.com/post-5351/
第二回:実存
https://portla-mag.com/post-5804/
第三回:虚構
https://portla-mag.com/post-7975/
第四回:ルサンチマン
https://portla-mag.com/post-9241/
第五回:ユートピア
https://portla-mag.com/post-9582/
第六回:アイデンティティ
https://portla-mag.com/post-10112/
第七回:刹那
https://portla-mag.com/post-10539/
第八回:散文