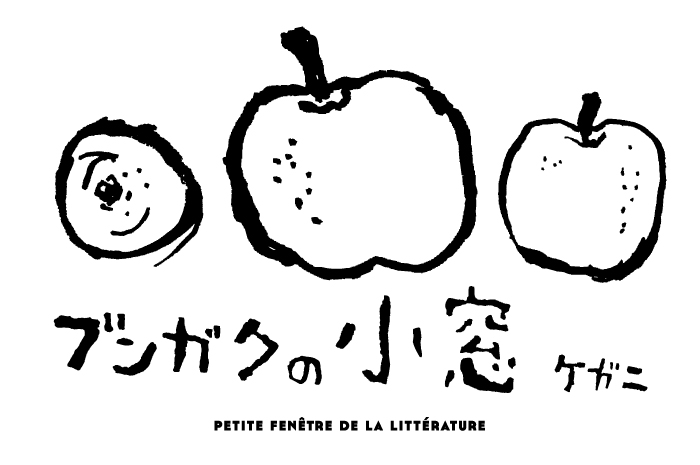こんにちは、ケガニです。
「ブンガクの小窓」、第二章。
前回編集長からだいぶハードルを上げられたのだけれども、かまわず平常運転で書いていくつもりである。どだい、専門家とかエキスパートとかいう肩書ほど信用ならねえものはないぜ、とつねづね思っている僕である。実際ブログなんてものは、面白いものを書くか、書かないかの勝負だ。もし面白くなければ、そっと、ブラウザの閉じるボタンを押してほしい。そして、僕と会ったらそんなことはおくびにも出さず、「連載、面白いね」と笑ってほしい。それが人情ってもんじゃあ、あるまいか。
————————————
今回のブンガク語は「実存」(じつぞん)。
なんだそれ、と思われる読者もいらっしゃるだろうし、ははーん、とうなずく読者もいるはずだ。じつはこの言葉、ある時期を境に一気に広まり、そしてある時期を境に急速に衰退していった言葉だからだ。それだから、ある年代以上の人にはたいてい通じるし、そうでなければ首をひねるような言葉、それが「実存」なのだ。
だが、この言葉はあらゆる人々にかかわっている。
どういうことだろうか。
実存とはなにか
初めにこの言葉の意味をざっくり述べてしまおう。
「実存」とは、「今、ここにいること」である。
もちろん、誰だってそれぞれ「今、ここにいる」だろうし、そんなことわざわざ言わなくても当たり前だ。ごもっともである。だが、実を言えば、その当たり前のことを「わざわざ」言わなければならなかった時代があったのである。
ある時代、それは第二次世界大戦のあと、1945年から60年代までのことだ。「実存主義」という言葉の下に、その時代の思想はひとまとめにされた。人々は「今、ここにいる」と声高に主張し、あるいは街角を占拠した。政治思想のようなものになりさえもした。それは大量殺戮の戦争によって奪われたものを取り返すためのスローガンだった。過去や伝統や秩序に飲み込まれてしまってはいけない、という主張を込めて、「実存主義」はスローガンとなったのだ。そしてそれはロックという音楽とともに、全世界に広がっていった。若者たちはみな口々に、「今、ここにいる」と叫び、もしくは歌った。単なるジャンルにすぎなかった「ロック」は「反抗」を意味するようになった。
いったい、実存とは何か。そして実存主義とは何だったのか。

「実存」という言葉の成り立ちを考えてみよう。
日本語に「実存」として翻訳される前、この言葉は、英語でいうexistence、つまり「存在すること」という言葉だった。だったらなおさら、「存在」という言葉でいいではないか。なぜいちいちブンガクっぽい新しい言葉を作るのか。それはこの語が示すのが、たんに「存在」することではなく、「現実に存在すること」だったからである。だから「実存」とは、「現実存在」の真ん中の二文字をとって作られた造語である。
「ペンが現実に存在する」と言ったとしよう。普通は、目の前にいわゆる「ペン」が「存在する」ということを意味するはずだ。
しかし、この目の前のペンは、本当に現実に存在しているのだろうか。
目の前にペンがある、ということを言うためには、そもそもこの「僕」が「ペン」を見ている、ということが必要なはずだ。「僕」が無ければペンも無い、というわけではない。もし世界から今僕が消えてしまったとしても、ペンは実際にはそこにあり続けるかもしれない。
だが、それを確認する誰かががいなければ、そこにペンがある、と言えない。言ったとしても、それは正しいとは言えない。
あらゆるものは、今ここにいる「僕」の存在によって存在を確かめられうる。
さらに言えば、「僕」という言葉すら実のところ代名詞なのだから、「僕」は正確には「今、ここにいること (もの)」ということになるはずだ。
「今、ここにいること」という存在のみがあらゆるものの存在を確かめうる唯一の現実存在である。
つまり、ここの、この、「実存」のみが、あらゆるものの存在を確かめうるのである。
実存主義の成立、そしてロック

なぜか。
それは戦争という危機の時代において、自分が存在することの意味を問う人々があふれたからだ。
既存の価値、制度、道徳、その何もかもを破壊しつくした戦争によって、アイデンティティさえも奪われた人々。こうした人々が「今、ここにあること」から全てが始まるんだぜ! と主張する思想に同調し、それを声高に主張した、というわけだ。
これが一般的に言う「実存主義」である。
このことを主張した有名な講演がある。それは哲学者サルトル (1905-1980) によるものだ。
「実存主義はヒューマニズムである」というタイトルの講演は、当時フランスで相当な人気を博し、当時の若者たちにセンセーションを巻き起こした。
(日本では『実存主義とは何か』の中に訳されて出版されている)

当時の状況を知るためにも、興味がある方は一読してみてはいかがだろうか。
さあ、この実存主義者の主張を、どこかで聞いたことがあるのではないか。
そう、「ロック」である。
ロックは「過去のもの、既存の価値観なんて関係ない!」「ここから全てが始まるんだぜ!」「社会にとらわれずに自分を貫こう!」、と歌った。
もちろんロックの成立根拠が哲学にあった、というわけではない。
こうした哲学の流れと (思想的な意味での) ロックの成立とは、切っても切れない関係にあった、ということだ。
こうしてみれば、そもそも社会のルールにまだなじみがない若者たちが、実存主義を標榜したのにも共感できるのではないだろうか。
ただし実は、ここにこそまさに実存主義の大問題がある。
実存主義への批判
「今、ここにあること」の実存に全ての存在が基づいている、というのが実存の思想であった。
しかしそのことはただちに、「だから過去や社会なんてどうでもいい」ということにつながらない。
いくら「実存」から全ての存在がスタートするとしても、そのことが「自分以外の全てに意味がない」ということにつながるわけではないからだ。
スタートは単なるスタートに過ぎない。たとえば、「「実存」というスタートに立たせてくれた過去に感謝すべきだ」、とか、「実存を与えてくれた絶対的な存在がいるはずだ」と考えたっておかしくないはずだからだ (それが実際に正しいかどうかは別にして)。
実存主義がある種の政治思想に変化して大流行したとき、「過去なんてぶっ壊せ!」という主張だ、と捉えた人が多くいる。
だがそれは間違いなのだ。
こうして、戦後の鬱屈した空気の中、実存主義は誤解をはらんで火花のように広まっていった。そして一般的に理解されるにしたがって、誤解を生み、批判され、攻撃された。結果として「実存」という語自体が衰退するに至ったのである。
そして今となっては、「実存主義者」をそのまま名乗る人間はほとんどいない。
どうだろう、今回は「実存」というなんとも不愛想な言葉を扱ってみた。
いかにもブンガクという感じだ。
わかったようなわからないような。
でも、だんだん寒くなる秋空の下で、こんなことをしかめっ面で考えてみてはいかがだろうか。
サルトルのように、苦い苦いコーヒーでも飲みながら。