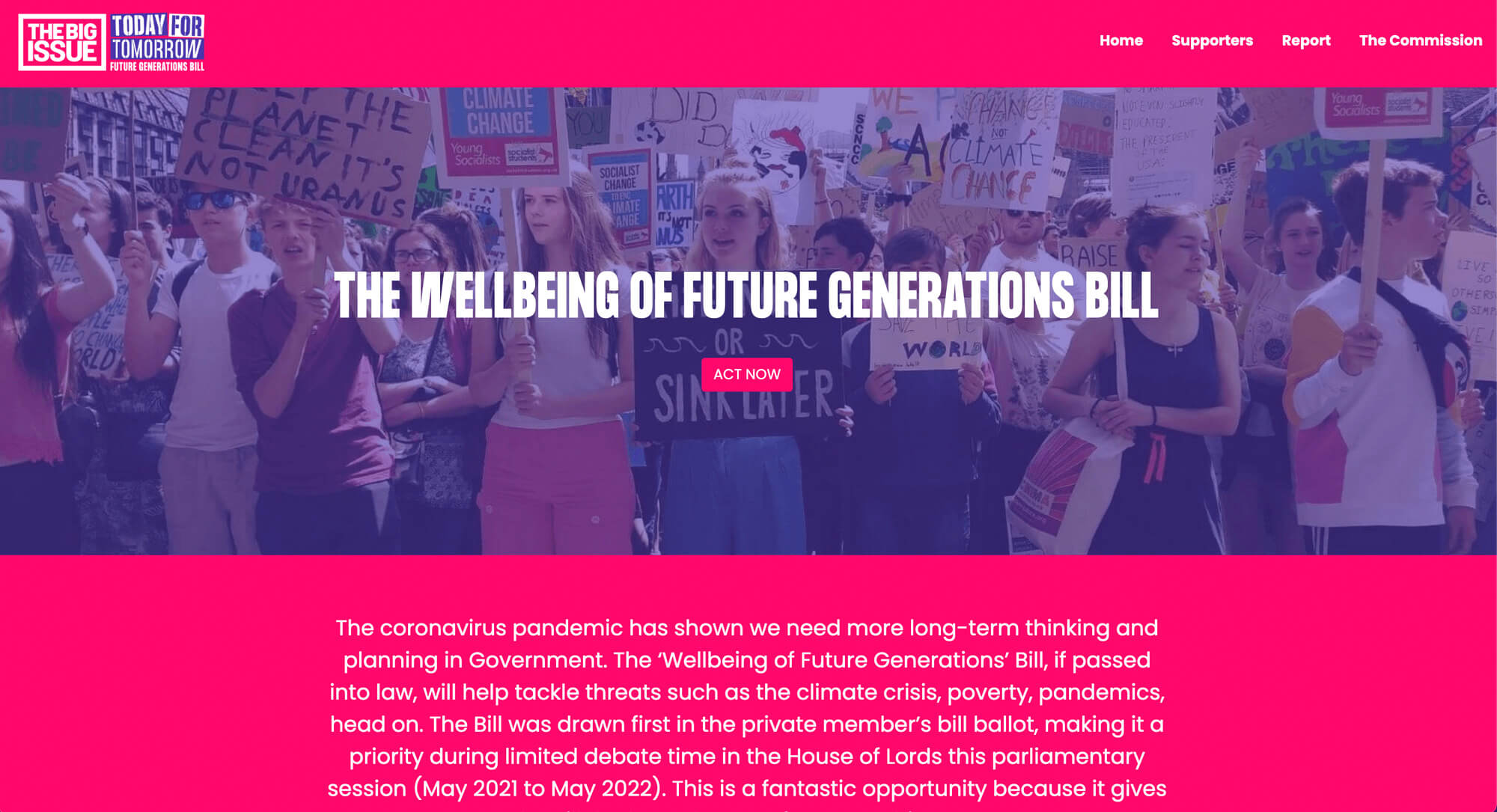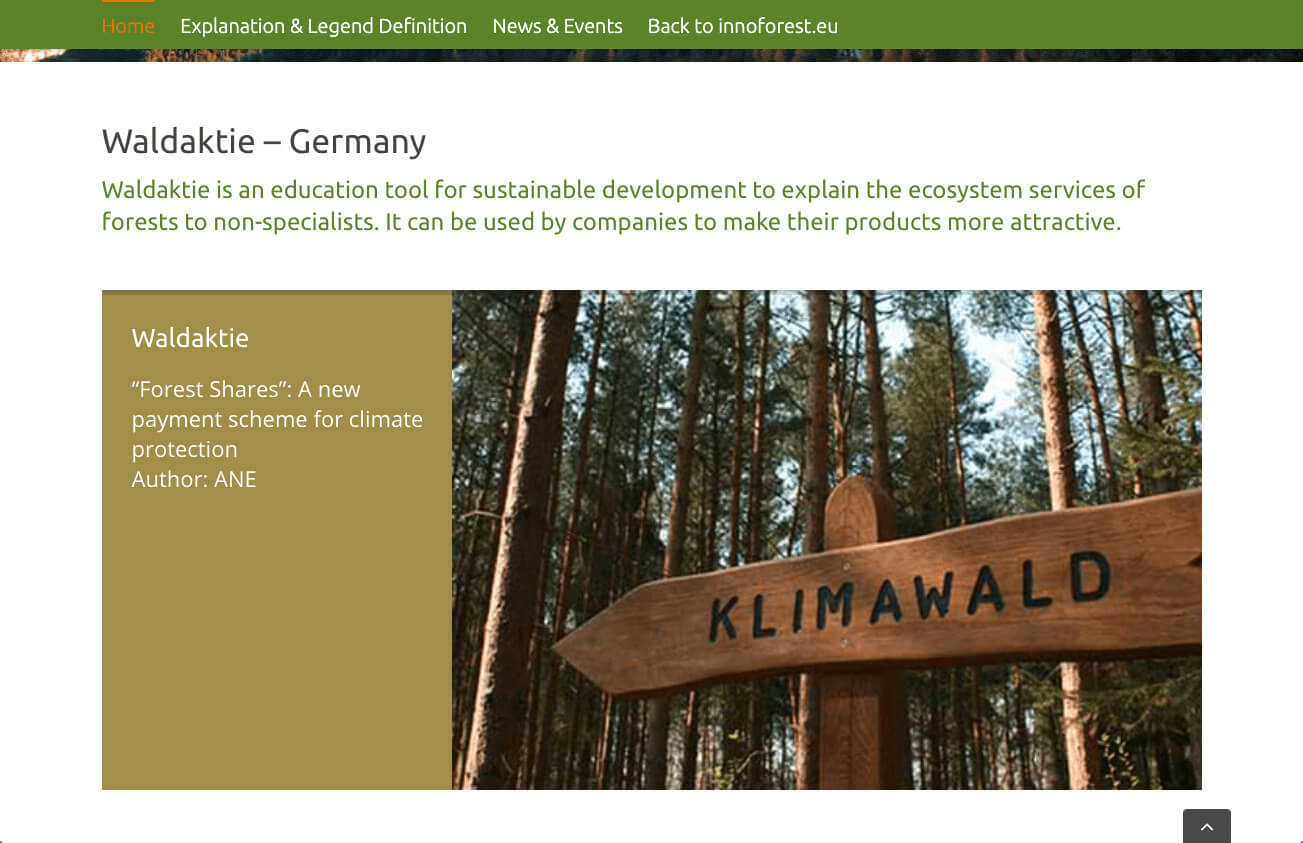筆者は2018-2020年にかけて、大学院留学のためフィンランドに住んでいた。2年間の森のくらしでは、苔やリスとの触れ合いや、たくさんの生命の気配とともに生きている実感があった。とりわけコロナ禍で人とのやりとりが消え去った最中、そのいのちの交感にとても気持ちが救われた。その触れ合いの歓びは、私をDeep Care Labという法人での、感情的な結びつきから気候危機に対峙するあり方の模索に導いた。必要なのは「こうあるべき」といった規範ではない、自然なケアの態度ではないだろうか。今、どのように<責任>を捉え直し、いち市民として自然環境や地球に関わり直せるのかを、フィンランドの経験や海外の事例をふまえて考察してみる。
書き手:川地真史

一般社団法人Deep Care Lab代表、京都在住。気候危機時代に、生態系や祖先、未来の子どもたちへの想像力をはぐくみ、ケアの実践へつなげる実験、企画や事業づくりを模索中。
自然と結びつくフィンランドの暮らしと気候危機
フィンランドは国土の70%以上を森林が占める、世界一の森林国。日本も同じくらい森や山は多いが、都市部で生まれ育ち、仕事もずっと東京。自然とともに生きている実感は全くなかった。フィンランドの首都ヘルシンキからは電車やバスで2、3駅いけば、またたく間に森に分け入れる。スマートシティ地区カラサタマからも、歩いて10分で森にたどり着く。そこは、子どもたちが果実を育てる食育空間Edible Forest(食べられる森)としても機能している。フィンランドでは「万人の権利」で知られているが、他人の私有地でも土地や森に入り、キノコやベリーを勝手に採ることも許される。友人は「祖父は何十種類ものキノコを見分けられる」と話していたが、きのこ狩りは夏のアクティビティであり、伝統文化だ。
この法と文化の絡み合いは、人ー自然の情動的な結びつきに影響を与えており、林業は主要産業として国の経済を支えている。自然環境は、本来誰かの所有に属さない、公共的なものである。フィンランドの「万人の権利」は所有ではなく”利用”の観点から関わりを生み出し、公共性あるコモンズとしての森林を成立させている。

しかし、綺麗ごとばかりではない。先日知人から聞いた話だが、大学キャンパスのあるOtaniemi地区では大規模開発が進み、住民の反対もむなしく木々は切り倒されているらしい。ここで、少し話を大きくしたい。現代は気候危機に直面している。先日発表されたIPCCのレポートで最も強調された点は、この原因の背景は人間である、との指摘だ。日本各地で起こる近年の豪雨災害はご存知の通りだが、なんと臨界点でもある気温1.5℃”の上昇により1.5倍の頻度・10%超ので豪雨が想定されている。またデータからも短時間の強雨、スコールの増加も確認できる。
わたしたちは自然との関わりに向き合わねばならない。COVID-19の原因は、経済発展のための自然搾取により行き場を失った野生動物と人間との距離の近接であり、根底には経済成長の神話と人間ー自然の二元論的な世界観から生じている。パンデミックと気候危機は、地続きの問題なのだ。
フィンランドの暮らしは自然との感情的つながりが前提にあり、節々でそれを感じることができた。では日本にいるわたしたちは、自然との関係をどう捉えているのだろう。もちろんコロナ禍でキャンプに行く人も増え、自然豊かな地域のワーケーションもトレンド、周りに花を買う人も増えた。とはいえ、人間のための「癒やし」や「娯楽」と見なすだけの場合も多いように感じる。
弱さを抱えるわたしとして、自然へ応答する
どうすればいいのだろう。もちろんトップダウンの取り組みは必要不可欠だ。フィンランド政府も森林保護区を増やし、植林・育林への政策を集中的に進めている。しかし、森林は公共的なものであり、政策も当然重要ではあるが、本質的にはその地域の人々がどう関わるのか、も問われる。わたしたちはそこに向き合わずに、お上まかせにしてきた結果、現状の限界を迎えているとも言えそうだ。
近年では、グレタ・トゥーンベリの呼びかけからはじまったFridays For Futureをはじめ、「未来世代のウェルビーイング法案」をイギリス政府に訴えるToday for tommorowなどの運動も盛り上がりを見せる。とはいえ、市民参加や公共性、コモンズの文脈において、市民の義務のように一人ひとりが上記の運動や、自然環境活動への主体的な参加を説くことに、違和感もぬぐえない。それは”強い”個人と自己責任から来る違和感だ。「各人が意志をもち自立した個人として行動せよ」は、”社会的状況に対して一人で決定し義務を負える”近代的・合理的な個人像が暗黙の前提に敷かれている。
この人間像の転換が必要ではないだろうか。強い個人として対峙するではなく、弱さの受け入れから始めることが重要だと提起したい。池谷は、ケアと脆弱性から人間の再考を迫る(※1)。人間は生まれたときも死ぬ間際も助けなしで生きられず、この意味でもケアしケアされる関係の中で生きるのが人間だ。特に「エコロジー的脆弱性」に注目したい。それは、人類が”自然に依存しなければ生きられない”弱さを浮き彫りにする。食べ物もスマホもすべて自然の生きものや鉱物の加工物であり、わたしたちのニーズは”彼ら”に依存しなければ満たされない。しかし近代はその弱さにふたをして、人間社会に閉じ、依存関係を切り離して自然をコントロール”対象”に貶めてきた。
だからこそ、わたしたちは弱さの前提に立ち直し、責任感覚を取り戻すことが求められている。責任とは、Response-ability=応答する能力である。極端にいえば赤ん坊が川で溺れていたら(=呼びかけ)、考えなしに手をさしのべずにいられない(=応答)ふるまいだ。気候危機でも川の氾濫や洪水は「地球からの呼びかけ」だと捉えられる。しかし、わたしたちは耳をふさいできたし、スケールの大きさにどう応答すべきか悶々している。國分功一郎は「自分が向かい合った出来事に、自分なりの仕方で応ずること」の重要性を指摘しているが、これをみると先のToday for tommorowは若者達の中で湧き上がったひとつの応答の表現だということが分かる(※2, p.5)。
しかし、それにはまず応答しよう、というモードが必要になる。「応答したいという気持ちが湧き起こってくる、文字通り責任を取りたいとbecomingする」と熊谷が語るように、プロセスを経て、責任主体へ”成りゆく”モードの変容が起こる(※2, p.400より)。責任を負うためのプロセスとは何か。ここでケアにもどり、手がかりを得たい。ノディングスは、ケアを気がかり・気にかける・世話するの3つの位相で捉える(※3)。それぞれのニュアンスは、以下だ。
気がかり: ある事柄に対して、重荷に感じたりや心配している
気にかける: ある人や対象に、関心や好意をもつ
世話する: ある対象に、責任を感じ世話を施す
前者ふたつは、情動的な感じ方であり、世話をすることはケアの実践であり「応答」にあたる、と言えそうだ。ケアの実践とは責任の実行なのだ。そして、ノディングスはケアへの動機が”おのずから”生じるものと捉えている。能動的な意志や努力では限界がある。湧き上がる気持ちから責任が生成されるのだ。さらに、その実践にうつるためには、他者の感じ方を自分の中に感受することや、自分自身がケアされた経験の記憶が重要になるとも指摘している。
これをふまえれば都市や地域には、まず第一に弱さの自覚とともに自然に対して情動的な結びつきや共感からケアの動機が育まれる空間が必要であり、その上でこれは自分でできるかもしれない、と多様なケアの応答への補助線が引かれていることが重要だと感じる。前置きが長くなったが、次にそうした「ケアの育み」「応答の補助線」の事例を一つずつ紹介したい。
都市を漂流しながら、新たな物語とデータをマッピングするOpen Forest
Open Forestはこれまでと異なる角度で都市のデータを収集する、参加型アートを活用した研究だ。この研究は市民が直接参加することを前提に、インタラクティブなインスタレーションに関わったり、ワークショップ形式のイベントに参加を通じて、新たな森のデータや物語を共に制作するものが多い。
森林のデータフローを探求する一連のインタラクティブなインスタレーション、パフォーマティブなアクション、そして思索的な研究手段で構成されています。このプロジェクトは、科学者、市民、センサー、環境データ、気候変動、樹木など、森林と異なるつながりを持つさまざまな主体間の関係を再考し、再配置するのに役立ちます。その目的は、主体についての物語を語り、彼らへのケアを実行できるような風景を広げることです。
一連の研究のいちプロジェクトであるMore-than-Human Dériveは、木々と多くの生き物からなる複雑な生態系である”都市の森”を漂い、人間以外の物語や視点の共有を通じて自然とのつながりを深めるもの。Dériveとは”漂流”を意味する。身体と五感を頼りに漂う中で、人間ならざる存在に自らをひらき、これまで聴いてこなかった声や、見えなかった視点を知る。都市にいながらに、都市自体が森のような生態系であることに気づき、データマッピングを通じて、木々や生きものへのケアの態度を育んでいく。
マッピングする「データ」は決して数値的なものだけを意味しない。わたしたちが感じたことがらや、物語であってもデータといえる。具体的には、参加者は実際に都市をねり歩き、木々との関わり合い、出逢った生物、そこで生まれた物語などをオープンソースの地図アプリケーションにマッピングするのだ。参加者は都市へのまなざしが異化され、収集されたデータは新しい都市構想の切り口や今後の作品の素材として活用される。現在はメルボルン、ヘルシンキ、バルセロナを中心にマッピングが行われている。
漂流とはその場に感覚を開き、都度ごとに踏み跡を刻んでいくことであり、目的志向ではない。とはいえ都市の生態系に気づくことを促したい。そこで、都市の風景の中にある、気づかれないような生き物や物、現象に気づき、注意を向けるように誘う、10のカテゴリーで「漂流の仕方」を提示している。例えば以下のようなものだ。
Becoming:見えないもの、聞こえないものに耳を傾け、同調する
Space-time時空間:空間と時間を異なる方法で理解する
Decentering the Human:人間中心主義と人間の例外主義を仮定しないこと
Sensemaking:異なる方法で感じ、考え、知ること
Webサイトにアクセスすると、それぞれの分類をもとにランダムな視点が提示され、漂流への補助線がひかれる。
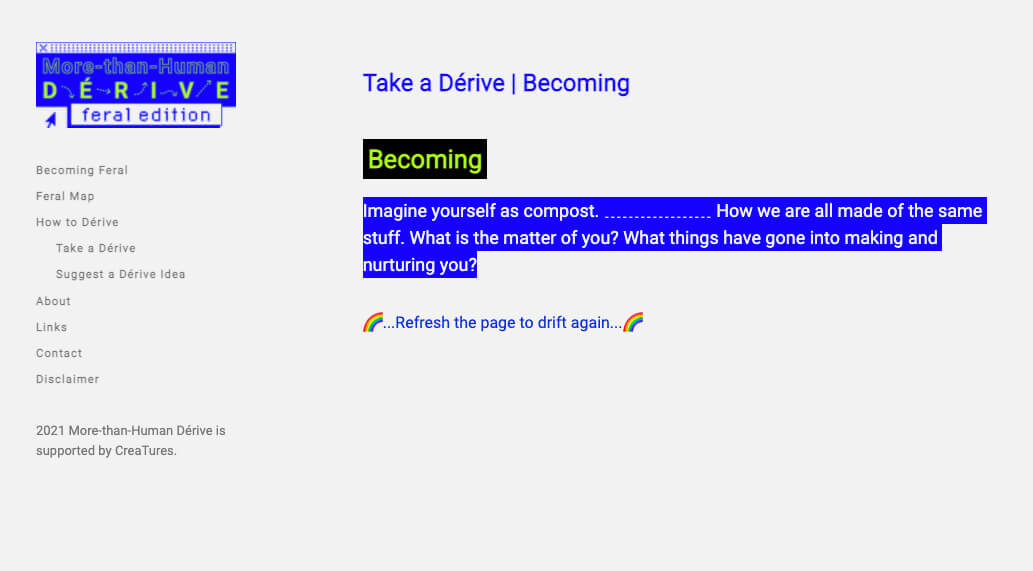
自分が堆肥になったと想像してみてください。……………いかに私たちが同じものでできているか。あなたは何でできているの?どんなものがあなたを作り、育んできたのでしょうか?
「あなたは木になる。木としてこれまでに何を目撃し、将来、何をしうる?」「植物の葉っぱを探しましょう。どのように呼吸しているか想像してみて。葉っぱのように呼吸してみてください。……………葉の表面にはどんなものが出入りしていますか?気体、液体、固体……。」「人間ではない二人の間にある”間”を見つける。その空間には何があり、何が通る?」……などの想像的な問いかけがなされる。
この問いに沿って、都市の異なる場所にいる市民がオンラインを介して参加する「漂流型ワークショップ」も開催されている。こうした遊び心あるアプローチから森との感情的な結びつきを生み出すことは、人々の責任の湧き上がりを促し、応答能力につながる。一方、そこからどのように私なりの応答を行うかは委ねられる。次に、気候危機の時代に再考を迫れられる観光と自然保護に不可欠な財政の切り口から、無数にあるひとつの応答の可能性を見ていきたい。
「森林株式」の財政スキームWaldaktieから、観光を通じて応答する
いかに自然環境の維持や再生に予算を投下していくのか。財政面は大きな課題である。とりわけ、いち生活者としてどう関わればよいのか、思いも至らない。もちろん「みどりの募金」のような純粋な寄付もあるが、他にどういう経済的な側面からの関わり方がありうるのだろうか。
Innoforestは森林管理の新たな関係者の提携・支払いスキームの確立などの政策やビジネス、ガバナンス・イノベーションから森林生態系を持続可能にする研究プロジェクト。その中の研究対象のひとつとして、ドイツのWaldaktieが挙げられる。これはツーリズムと連動し、森への投資を通じてCO2ニュートラルな観光を実現する「森林株式」の支払いスキームである。
気候保護のための新しい支払いスキームで、主に観光客が「森林株式」を支払う(購入する)ことで、休暇中に排出したCO2を補うことができる。
近年、エコツーリズムは拡がりを見せているが、そもそも観光自体に移動も伴いCO2を大量に排出する。ジャカルタのバレンシアでは観光客のCO2排出量を測定する取り決めをつくったり、フィンランドでは、CO2の排出量で宿泊費用が変わるホテルもある。この支払スキームが秀逸なのは、観光客を対象にし、自身が出したCO2排出の事実に向き合う機会をつくった上で「排出しちゃった……」という負債感覚を引き受けるきっかけを作り、この状況に対する応答のかたちとして”森への投資”に転換する仕組みだ。なぜ森への投資か、といえば森林自体も「カーボンシンク」とよばれるCO2を吸収してくれる働きをもつ存在だからである。
具体的には、1口10ユーロのフォレストシェアを2口購入すれば、10平方メートルの面積に木を植え、手入れをすることができ、休暇中に排出される二酸化炭素を相殺することができる。たとえば「4人家族でメクレンブルク(ドイツ)に2週間滞在した場合、車での移動、宿泊、レジャーなどを含めると、約200kgの二酸化炭素が排出され、10平方メートルの森林を新たに再生すると、成長段階で約1立方メートルの木材のバイオマスが生成され、平均925kgのCO2を吸収することができる」とのことだ。https://www.auf-nach-mv.de/waldaktie-wird-umgebaut
また、購入者は自分で木を植えることもできる。Waldaktieは、森林の生態系サービスを一般市民に説明するための教育機会でもある。パンデミックの終息後に、観光がどう変わっているのかわからないし、環境負荷の高い飛行機に乗ることの是非も広く議論されはじめている。しかし、観光は環境への関心に伴わず、アクティビティとして行われ続けるだろう。
このスキームは、広く森林への投資を行うための汎用的な可能性も秘めている。もしも入湯税のように、森林シェアが森林税になったら?といった思考実験もできる。一方で、それを現状の状況や深いコミュニケーションなしにシステマティックに実装すれば「お金を払えば気にせず観光できるんだ」と安易な免罪符に回収されるリスクも孕む。スキームだけで成り立たず、認知の際のコミュニケーションや対面での理解形成などタッチポイントを通じて、責任が生成されるプロセスづくりも両輪で進める必要があるように思う。
むすびに|500
フィンランドの自然との精神的な結びつきある暮らしから、気候危機に話を広げてきた。気候危機は公共的な問題である以上、市民としての関わり方が問われるが、義務感ではなく弱さの気づきと情動から、湧き上がる責任主体への変化によって、各々ができる応答を行う可能性を論じてきた。これは、一見遠回りで曖昧にみえるかもしれない。しかし、実際に人間は合理的で意志を元にした生きものではない。2つの事例は、それぞれ責任生成のプロセスに足場をかけ、応答の補助線としてのスキームを提示した。それを受けての「わたしなりの応答」の仕方は無数にある。私でいえば、法人活動でのワークショップやプログラムを通じた学びの場づくりも応答のかたちだし、その他、畑を借りて食から暮らしを作り直そうとする最中だ。
とはいえ、こうした応答が適切なのかも分からない。理解を超えた複雑な状況で、”正しい”応答は存在しないとも思う。迷い、葛藤し、逡巡してばかりの日々である。ゆえに、その分からなさを手放さずにたゆたい続けること、つまり弱さを引き受ける強さが必要だと思う。その強さを持つためにも、周囲の人とのゆるやかに話し合い続けている。小さいがこれも大切な応答であると信じているし、それと同時に、弱い私だからこそ一層まわりの支えがいるのだろう。
リファレンス
※1『脆弱性、ケアと道徳教育, 池谷 壽夫』
※2『<責任>の生成ー中動態と当事者研究, 國分功一郎, 熊谷晋一郎』
https://www.shin-yo-sha.co.jp/book/b548211.html
※3『ケアリング 倫理と道徳の教育――女性の観点から, ノディングス 立山善康他訳』