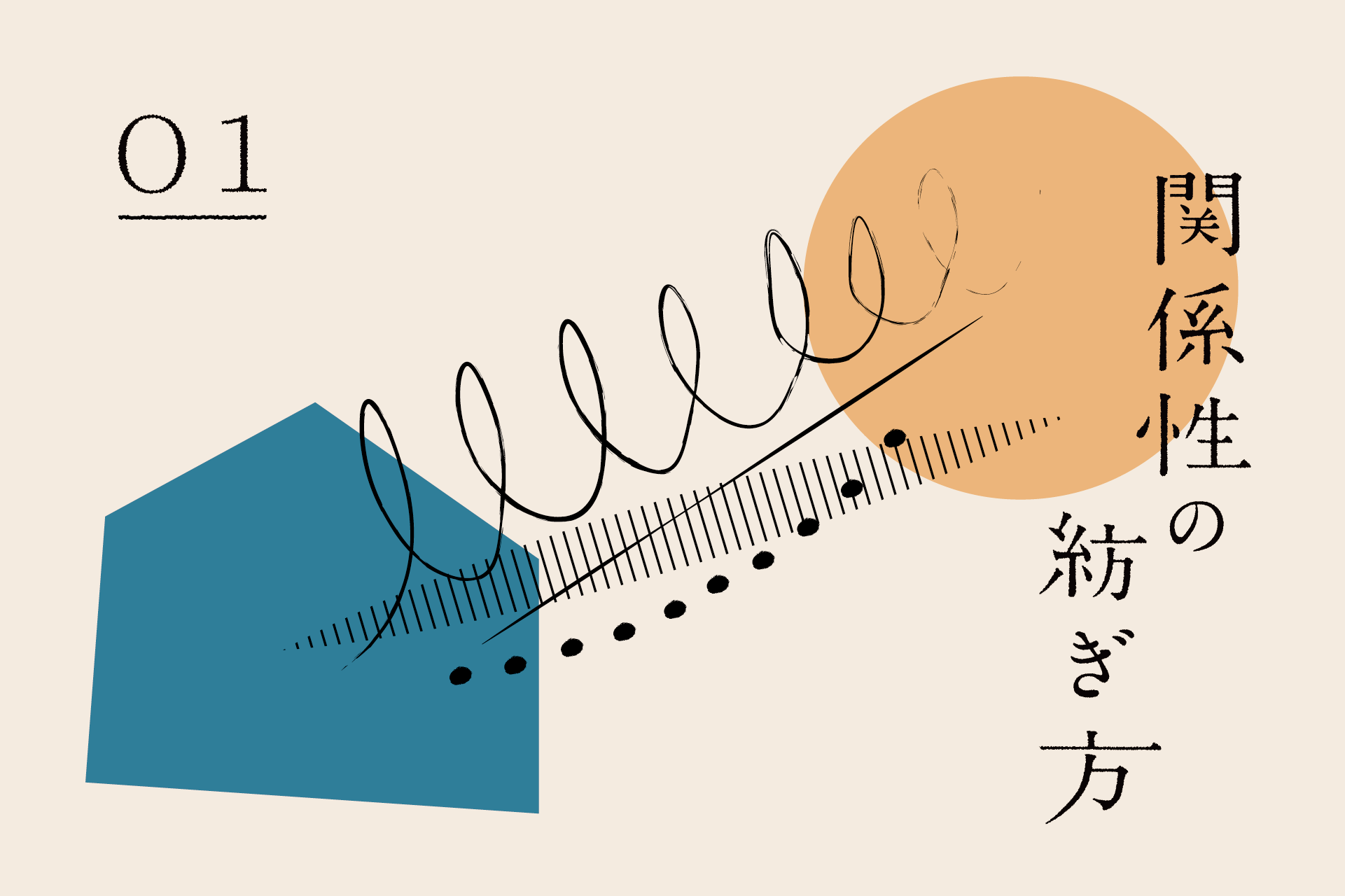「ふたつの間にある、無数のいろいろのために」という言葉を掲げる出版社があります。京都を拠点に本の企画や編集を行う「出版社さりげなく」は、2022年7月現在までに9冊の本を出版。例えば、文章が載っているのは最初の数ページのみで、他は白紙で構成された『渡り鳥』(岩谷香穂、2020年)や、4つのテーマについて考えた「結果」ではなく「過程」を記した雑誌『思考記 2020-2021』(2021年)など。そのどれもが思わず手に取りたくなる人懐っこい佇まいながら、答えを提示せず、読者に解釈を委ねる本が並びます。
今回PORTLAで新たに立ち上げる連載「関係性の紡ぎ方」は、絶対にわかりあえない存在である他者と、それでもよりよい関係を築くためにはどうすればいいのか、その手がかりを見つけるための企画です。その答えはひとつではなく、まさに「ふたつの間」に「無数」に存在しているはず。出版社さりげなくのサイトでこの表現と出会った時から、稲垣さんに最初にお話を伺おうと決めていました。
稲垣さんと、さりげなくメンバーを含む本の作り手、書き手、読み手、それぞれとの関係を紐解く中で見えてきたのは、わからないことをわからないまま扱う強さでした。それは決して無責任な行為ではなく、全てを理解することは不可能な他者を尊重する姿勢であり、自分本位な視点で語らないという意思でもあります。相手のことなんてわからないのが当たり前のはずなのに、つい私たちは知ったかぶりをしたり、「わかってくれるだろう」と期待したりしてしまいます。でも、本当はいつだって「わからない」から始めていいんだということを、稲垣さんとさりげなくの本は教えてくれます。
関係性の紡ぎ方
Happiness only real when shared. ー幸福が現実となるのはそれを誰かと分かち合った時だ(『イントゥ・ザ・ワイルド』)。誰かと関係を築き、大事なものを分かち合うことは、多くの人にとって人生の喜びのひとつではないでしょうか。新型コロナウイルスによって人と会う機会が制限されても、国籍やセクシュアリティ、思想、年齢などの枠組みに無理やり押し込められそうになっても、私たちは他者との出会いなしで生きていくことはできません。自分と異なる誰かに触れることは、新しい世界にそっと足を踏み入れる豊かな心の旅であると同時に、人を分断しようとする大きな力から逃れる術にもなるはずです。本企画は、ひとつとして同じ形はない誰かと誰かの関係性を照らしながら、他者とのつながりについて思索を巡らせる試みです。
稲垣佳乃子プロフィール

1993年、神戸市生まれ。さりげなく代表、企画・編集。25歳でさりげなくを立ち上げ、全ての本の企画・編集に携わる。作家の思いを見出し、何を伝えるべきかを考え、本だから表現できることを常に模索しつづける。
さりげなくの文化を作ってくれる人と仕事がしたかった
出版社さりげなくを設立する前に、もともと古本実加さん(装丁家で現さりげなくメンバー)と「ふたり」というユニットで活動されていたんですよね。
はい。でもそのころは出版社を作ろうとは思っていなくて、とにかく企画とデザインで面白いことをやりたいと思っていました。当時から紙媒体が中心でしたが、二人とも別の会社で働きながら活動していたし、出版社の話は一切していなくて。「『ふたり』がいつか企画とデザインの会社になるんかなあ」くらいのぼんやりした感じでした。

仲西森奈さんの短歌を読んで本にしたいと思ったことがきっかけで、出版社を立ち上げたと別のインタビューでおっしゃっていました。ビビッと来たものがあったんですか?
そうですね。とにかく「めっちゃいい!」って思いました。もともと仲西さんは古本さんの友だちだったので、小説とか他の作品は読んでいたんですけど、短歌を読むのは初めてで。あまりに良かったから、「もうこれは本を作るしかない!」って(笑)
出版社を始めることに対する怖さはなかったですか?
一から営業していけばきっと大丈夫だろうと思っていました。「ふたり」として活動していた時にZINEを作っていて。ZINEを取り扱ってもらうために、本屋さんに自分たちで営業しに行っていたんですよ。そこで「面白いね」って応援してくれる本屋さんが結構あって、本屋さんとの関係性を作れていたことが大きかったですね。
それで出版社さりげなくを立ち上げて、株式会社にしたのが2021年?
はい。仲西さんの歌集『起こさないでください』を2019年に出版した時に出版社登録はしていたんですが、2021年までは会社ではなく私の個人事業としてやっていて。でも最初からいろんな人と仕事をしていたので、さりげなくで稼働している人は、常に二人以上はいましたね。

最初は「ふたり」の延長のような形だったのかと思っていたのですが、ちょっと違うんですね。
そこは微妙なんですけど、ユニットだからとかではなく、その作品のデザインに適している人を常にアサインしていて。それが古本さんになることが多かった、という感覚の方が正しいかもしれません。だから、「ずっと一緒にやろうね」みたいな話は全然していなくて。古本さんは装丁家としてビッグになりたいという思いがあり、私は本の編集者として頑張りたい思いがあり。ちょっと表現が難しいのですが、お互いその道を行くために、利用し合っているみたいな感じなんです。
だから、『起こさないでください』の時も、古本さんには話をせずに作り始めて。装丁家を決めるタイミングが来て、誰にお願いするかを考えた時に、「これはやっぱり古本さんだな」と思って投げかけた形ですね。
「一緒に作ること」が前提なのではなく、あくまで作りたいものが先にある。
そうですね。株式会社化するタイミングもまさにそれで。出版社さりげなくをいいものにするためには誰が必要か考えた時に、絶対社内に装丁家がいた方が会社として良くなると思って。「じゃあ古本さんは装丁家としてビッグになりたいし、win-winだな」って。それを伝えた上で、古本さんを誘いました。
お話を聞いていて気づきましたが、装丁家が社内にいる出版社って少ないですよね。
もともとサイのマークで知られる晶文社は、30年近く本のデザインをほぼ全て装丁家の平野甲賀さんに頼んでいたんだそうで。だから、甲賀さんは晶文社に所属していなかったけれど、晶文社の本を何千冊とかデザインしているんです。今、本の作り方としてよくあるのが、出版社が単発で有名な装丁家に頼む構造です。そうすると、当然その本単体で見れば立派なものになる。でも当時の晶文社と甲賀さんの関係は少し違ったんじゃないかと想像していて。晶文社はどういう出版社が世の中に必要かまで考えて甲賀さんに依頼していたと思うし、甲賀さんも晶文社がやりたいことをわかっていたと思うんです。だから、やるならそういう形がいいなって。
本単体のことだけではなく、出版社の方向性まで理解してくれる人と一緒に仕事がしたかったと。
その本自体の価値も大事だけど、その出版社がどういうことをやりたくて、どういう文化を作っていきたくて、読者とどういう関係性を築いていきたいか。そこまで考えてくれる装丁家と仕事をするには、やっぱり中にいてもらう必要がありそうだと当時思ったので、入ってもらいました。
「作り手の自己主張は必要ない」とメンバーが教えてくれた

装丁部の古本さん以外にもメンバーがいらっしゃいますよね。
はい。編集部、デザイン部、経理部。あと『納豆マガジン』(納豆の面白さを紹介する納豆カルチャー誌。2021年にvol.1を発“酵”)を作っている納豆部も。
「納豆部」って名前、めっちゃいいですよね。
「本当にあるんですか?」ってよく連絡がきます(笑)。でも、納豆部を含めていろんなメンバーと仕事をしていても、チームの運営に関しては、私はまだまだです。もっと歳を重ねたら、今相手のどこまでを理解して、相手のどこからは理解しなくていいかみたいなバランスがとれる気がするんですけど。同じチームで働く相手には、こうなって欲しいという期待感がまだすごく強い。それをそぎ落としていけるようにならないと、チームがうまく成り立たないというか。まだ信頼しきれていないのかなあ。
「さりげなくラジオ」の中で、年2回発行の定期便を作った時のお話をされていましたよね。稲垣さんは1号作って、次号からはすぐ他のメンバーに制作を任せたというお話を聞いて、他の人に丸々パスできるのは、相手を信頼しているからかと思ったのですが。
うーん、確かにそれは信頼していますね。そういう自分でありたいって思っているからかもしれないですけど。会社の代表をやっているからってすべてお見通しなわけではなく、ずっと模索している感じです。
ちょうど古本さんの産休発表の回で、仕事を続けたがっていた古本さんに、稲垣さんが絶対に休むよう伝えたというお話もありました。
だって、「これからすごく長く続けていきたいさりげなくの、たかが1~2年休んだところでなんになんねん!」くらいの感じなので(笑)。それに、やっぱり自分のことを大事にした方がいいから。仕事って、基本的に他人を大事にしないとできないことだと思うんです。本づくりなら、まず作家さんを大事にしなくちゃいけないし、装丁家からしたら編集者も大事にするべきだし、印刷会社さんも本屋さんもだし、本屋さんは何人もいるし……。大事にする人が多すぎて、そんな状況で自分を大事になんかできない。だから、自分を大事にすべき時は、絶対に自分を優先した方がいいという判断ですね。
これまでは稲垣さんから他のメンバーへのアクションのお話でしたが、反対にさりげなくチームのみなさんからの言動で影響を受けていることもありますか?
ありすぎて、どれが誰の影響かもわからなくなるくらい影響されまくっています(笑)。強いて言うなら、古本さんは「古本実加が装丁したということが見えない方がいい」とずっと言っていて。本屋さんに並んで、読者が手に取った時点で、作り手がどういう人かなんて誰も必要としない情報で。「その本が何を伝えたいかを読者が受け取るから、そこに作り手の自己主張はいらない」というのは、私も編集をする中で思います。
作り手が見える必要はないと。
編集者や装丁家が作家と同じぐらいの並びで出てくるような本も多いですけど、その必要はやっぱりなくて。まず作品が一番前に出るべき。その後ろに作家がいて、もっと離れたところに編集者と装丁家がいる、という意識を持っています。そこは、古本さんがよく言語化してくれていたから、私も再確認できているところはありますね。

作家との「わからない」の問答から本が生まれる
作家さんと良い関係を築くために意識していることはありますか?
編集者だったらみんなそうだと思いますけど、作家さんに合わせますよね。どういうやり方が合っているかはすごく考えるし、作家さんから「もっとこうして欲しかった」とか言ってもらえることもあります。
そういうフィードバックがあるんですか。
そう。だからめちゃめちゃ勉強になります。もちろん努力はしますけど、実際のところどうすればよかったかはわからないので。だって他人じゃないですか。そこの関係性を雑にせずに、ちゃんと言ってくれる方がいるのはありがたいですよね。
こちらが一方的に動くというよりは、お互いに感じたことを持ち寄るような感覚なんですね。
テレビに出てくるような少年漫画誌の編集さんとか、「これは次にこうした方がいいと思います」ってズバッと言ったりしますよね。それはそれですごいと思うのですが、何が正解かなんてわからないじゃないですか。無数にパターンがある中で、私ははっきり「これだ!」みたいなことは言えない。編集者に答えはないし、作家にも答えがないから本を作っているので、「もしかしたらこういうことを言いたいのかもしれない」みたいなことを、一緒に考えるっていう関係性なのかなあ。
だから、作家さんに「どう思いますか」って言われても、「いやー、まだわかんないですね」って言っちゃうんです。「まだ言語化できていないです」とか言いながら、思っていることを話すと、作家さんも思っていることを話してくれて、その繰り返し。だってわからないことばかりですよね。
確かに、何もわからないですよね。
何もわからないんです。何がいいか悪いかもわからない。誰かを傷つけたくないのはもちろんだし、愛を持って作りたいって気持ちは共通認識としてあるけれど、正解がある本を作っていたらそれこそHOW TO本になっちゃうし、そういう本を作りたくないって思っている出版社なので。「わかんないですねー」「わかんないですねー」「わかんないですねー」……進まん!みたいな。
(笑)。でもそういうところから、企画のヒントが生まれたりしますよね?
そうですね。作家さんと「わかんないですねー」の問答を続けているうちに、「あっこういう話がいいかもしれない」とか「この作家さんはこういうところを見ているんだな」って気づいたりして。じゃあこういう本を一緒に作りたいなって思い始めて、それを深掘りしていく感じかもしれないです。

さりげなくさんの本って、アイデアがすごく面白いですよね。『渡り鳥』を手に取った時に驚いたんです。数ページしかテキストがなくてそのあとは全部白いページで、閏年しか出さないというのもユニークだし。そういうアイデアも作家さんとの対話から生まれるんですか?
『渡り鳥』に関しては、著者の岩谷香穂さんと、閏年がなんで現れるのかをレシートの裏とかに計算して遊んでいたんですよ。「なんで現れるん?」「4年で1日ってどういうこと?」とか言いながら。そういう話をよくしていたので、香穂さんと本を作りたいと思った時に投げかけてみました。閏年をテーマにして、タイトルは『渡り鳥』、「見えないものと見えるもの」のことを書いてもらおうと。
作家さんとの話がベースにありつつ、アイデア自体は稲垣さんから出ることが多いですか?
うーん、最終的にこちらのアイデアのように見えるだけで、作家さんから出ていることが多いと思います。あと、よくアイデアに注目してもらえるのですが、それを一緒に形にしてくれる作家さんの方がやっぱりすごいです。実際にいい本にするには、作家さんがいないとできないから。
それに、なんだろう……アイデアというよりは解釈なのかな。アイデアはポンって浮かぶイメージがありますけど、そういう感じではないですね。
見え方や視点といった方が近い?
そう、視点のことですよね。私の解釈に作家さんの解釈が合わさるから面白いものができるんだと思います。視点がもうひとつ増えるイメージです。
読者の受けとめ方はそれぞれでいい

読者ってどんな風に想定されていますか?何歳くらいの、こういう人に読んで欲しい、みたいなことは考えているのでしょうか。
ないです!全く、想定が。
えー!では、本当に「自分が作りたい本」からスタートするんですか?
それが多いですね。あとは身近な人が面白いと思うかどうかぐらい。例えば花辺(出版社さりげなくが事務所を構える場所。他にもハーブの店や喫茶室がある)にいる人たちが「面白いね」って思うかとか。でも、最初からそう考えていたわけでもなく、本を作る中で変わってきた部分もあります。例えば『渡り鳥』は、20代あたりの若い年代が読者層かと思いきや、実際は50代や60代の方も買ってくれていて。それってすごく面白いなと思いました。大事にしたいことや大切にしたい想いは年齢関係ないんだなって。やっぱり人類だから。
「人類みな兄弟」じゃないですけど、共通する感覚があるんですね。
そうそう。人類みな、共通している部分はある。きれいなものを見たら、子どもも若者も大人もおじいちゃんも「ああ、美しいな」って、それぞれの視点、それぞれの解釈で感じるから、そこには普遍的な美しさがあるはず。そういうことは結構考えています。

さりげなくさんのサイトにある「AでもBでもなく、じつはそのふたつの間に豊かなものがある」という言葉が素敵だなと思っていて。何かと何かの間の物語を大切にしたいという思いが、刊行物にも表れていますよね。
うれしい!ありがとうございます。
一方で、そういう物語って、わかりやすい起承転結がなかったり曖昧さを内包している分、下手すると、読者が置いてきぼりになる危険性があるじゃないですか。それを明文化して「こういうものを作りますよ」と伝えることって、読者がちゃんと受け止めてくれる信頼感があるからこそできるのかなと思っていて。その信頼感ってどういうところから生まれているんですか?
うーん……難しい質問ですね。まず前提として、受け止められても受け止められなくても、たぶん本を作るんですよ、私は。昔は「何が正しいかわからないけど自分たちはこう思う」を形にしたのが本だったと思うんです。それが本当に正しいかどうかは、読者が判断してくださいって委ねるのが、本の役割だったはずで。でも最近は、読者の感情や行動まで決めようとする本が多い印象があって。「泣ける!」とか「親子で読める!」とかもそうですよね。
確かに「何回泣ける!」とか、本屋さんのポップでもよく見ます。
でも、「私はこれはなんとなく違うな」って感想を持つことだって、その本を受け止めたことになると思うんです。それなのに、ポジティブに共感しないと受け止めたことにならない本が多すぎて。「面白くなかったな」って思うのも一感想ってことを許容していかないと、もうどんどんセグメントされた本になってしまうんじゃないかなと思っています。
うちの父なんて、さりげなくの『Same Pose』(鈴村温、2020年)や『思考記 2020-2021』を見て「こんなん誰が読むねん」とか言うんですよ(笑)。でもそれも一つの反応じゃないですか。こちらがコントロールできないことだから、「あとは読者の好きにしてください」って気持ちです。
ポンッて出して、あとはご自由にどうぞという。
そうそう。食べ物と一緒ですよね。その人がどういうものを食べてきたかで、カップラーメンがおいしいと思う人もいれば、フレンチが好きな人もいるわけだから。その時々の自分たちなりの「わからない」を積み重ねた集大成みたいなものを出して、あとは委ねていく。一見雑に見えるかもしれないけれど、雑ではない。それが、読者を信頼している行為だと思っています。